金融商品を評価する際、投資金額と比較してどれほどの損益が発生したかを測る指標として、利回りが用いられることが多くあります。
利回りの考え方には「単利」と「複利」があり、同じ金融商品でも単利的に運用するか、複利的に運用するかで資産の増え方が大きく変わってくる場合もあります。
そこで今回は、投資で特に重要視される「単利」と「複利」の違いや計算方法、投資に活かすうえでのメリット・デメリットなどについて解説します。
単利と複利の違い
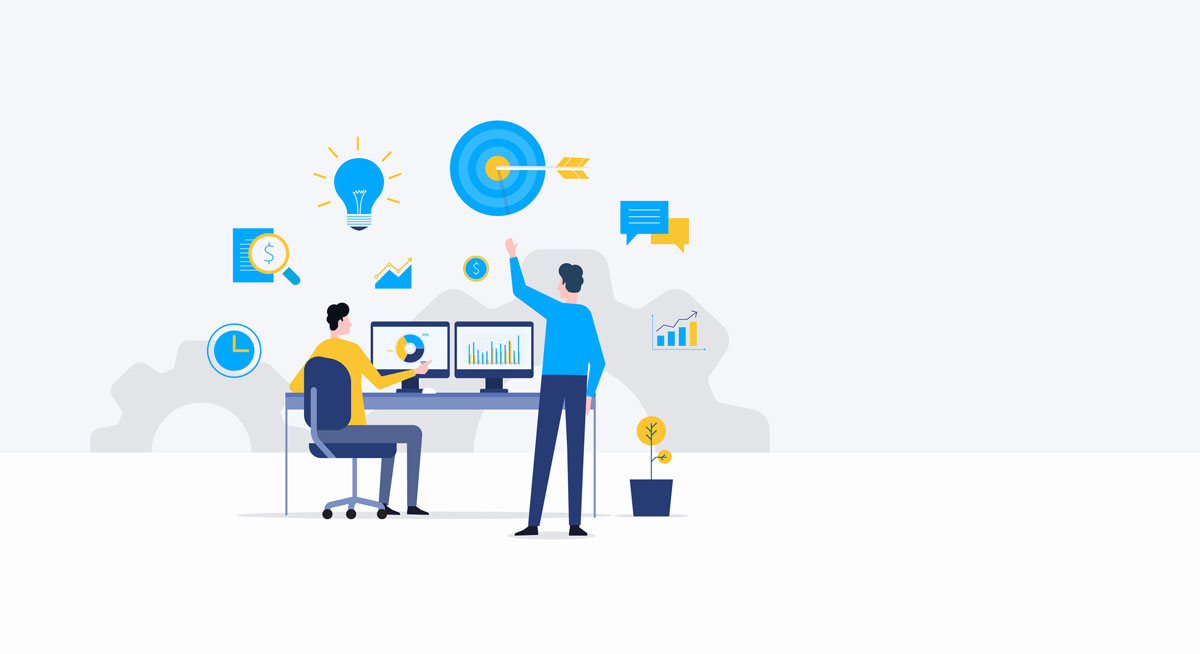
単利的な運用とは、利益を投資元本に組み入れることなく(再投資することなく)、投資元本部分のみを運用し続ける運用方法です。利益が発生しても都度受け取るようなイメージとなるため、投資元本部分は増加せず、複利と比較して資産の増え方が弱い傾向があります。
一方、複利的な運用とは、利益も投資元本に含めて運用する運用方法です。利益が発生した時に、それを投資元本に組み入れる(再投資する)運用をするため、単利よりも資産の増加スピードが格段に早くなる傾向があり、この効果のことを投資の世界では「複利効果」と呼びます。
利息の計算方法
単利により資産を運用した場合の計算式は「元本×(1+利回り×運用年数)」となります。
例えば、元本が300万円で利回り3%、10年運用した場合、390万円の資産が築けます。(税金の計算は含んでおりません。)
一方で、複利による運用の計算式は「元本×(1+利回り)^運用年数」となります。
上記と同じ300万円を利回り3%で複利運用した場合、10年目で約403万円となります。(1年複利計算の場合。税金の計算は含んでおりません。)
なお、当然ですが、運用年数が20年、30年と長期化するほど、複利と単利では運用による効果の差は開いていきます。
複利による長期投資のメリット

複利による長期投資のメリットは、投資の効率性や運用方法の簡単さにあります。以下に具体的なメリットをご紹介します。
投資の効率が高まる
単利運用より複利運用の方が投資効率が向上します。先に紹介した300万円を利回り3%で10年間運用した場合、単利と複利で約13万円ほどの差が開きました。これを長期間続けると、その差はさらに開きます。
資産運用は早いうちに、できるだけ多くの元本を投資した方が複利による恩恵を受けられます。20年、30年先の老後や将来を見据えた若年層の投資ほど、年齢を重ねた後に効果を得られるはずです。
再投資により複利効果が活かせる
再投資とは、投資において得た利益を手元に引き出すのではなく、再び投資資金として加えることを指します。
これは一見面倒に見えますが、現在多くの証券会社ではこの再投資を自動化できます。例えば、ある証券会社では再投資型の投資信託を選ぶことで自動的に再投資が可能です。
このように、運用に手間がかからないことがメリットのひとつです。
インフレに強い
複利運用はインフレに強い点もメリットです。本記事を執筆している2023年4月時点では、日本国内はインフレ(物価上昇)が続いており、このインフレ率を超えるスピードで資産運用を進めなければ、資産価値が目減りしてしまうことになります。
たとえば、普通預金にお金を預けて0.001%の利息をもらったとしても、インフレによる物価上昇率が2%もある場合は資産価値が目減りしてしまいます。
一方、金融商品で複利運用すれば、3%以上の利回りも期待することができます(損失が発生することもあります)。将来のインフレに備えるのであれば、複利効果を活用した資産形成は検討の価値があります。
複利による長期投資のデメリット

複利による長期投資のデメリットはそれほど多くないものの、以下の2点について注意しておく必要があるでしょう。
長期間資産を動かせない
複利の恩恵を受けるには、長期間に渡って資産を動かさない(換金しない)でおく必要があります。そのため、投資資金を切り崩して使うことは推奨されません。
長期間投資を行う際は、生活費など必要なお金は投資にまわさないという鉄則を守りましょう。
複利効果のメリットを得られないこともある
投資の成功が保証されていないように、複利効果も必ずプラスの効果が保証されているものではありません。不況に陥れば、当然リターンがマイナスになることもあり得ます。
単利運用の場合、利益が発生すればそのお金を手元に残しておくことができますが、複利運用の場合、得られた利益も投資元本に組み入れて運用するため、相場下落局面ではその影響をより大きく受けてしまいます。
とは言え、複利運用の効率性が高いことは変わらないため、余剰資金を複利運用し、分散投資などによってリスクを低減させることが一般的なリスクヘッジの方法となっています。
複利を活かす方法

複利を活かすには、以下の方法を実践することをおすすめします。
できるだけ長い期間つみたて投資をする
複利の効果を活かすためには、できるだけ長期間つみたて投資をすることをおすすめします。
先述の通り、複利の効果は運用期間が長いほど高まるため、若いうちから地道に投資すると、将来受け取る金額を増やすことができると考えられます。
少額で良いので、余剰資金があればまずはつみたて投資をはじめてみると良いでしょう。
元本には手を出さない
複利運用をしている間は、元本に手を出さないことは鉄則と言えます。
複利運用は元本が大きければ大きいほど効果を発揮します。そのため、せっかく増やした元本を換金して減らしてしまっては、効果が減少してしまいます。
元本には手を出さなくて済むように、生活費と余剰資金の割り振りを計画的に行いましょう。
72の法則を活用する
複利運用によって投資資産を2倍にするためにかかる年数をシミュレーションするためには、「72の法則」という簡便法が活用できます。
計算式は「72÷運用利回り≒元本が2倍になる年数」で見積もることができます。たとえば、運用利回りが3%の場合、元本を2倍にするにはおよそ24年の期間が必要と算出されます。
この72の法則を使えば、自分が目標の資産額までにどの程度の利回りで、およそ何年必要なのかを知ることができます。
126の法則を活用する
一度にたくさんのお金を投資せずに、少しずつ着実に投資したい方は、元本が2倍になる期間(年単位)がわかる「126の法則」の活用がおすすめです。
毎年一定金額をつみたて投資した場合、投資元本が2倍になるまでのおよその年数を計算するには、「126÷運用利回り≒元本が2倍になる年数」という計算式が成り立ちます。
たとえば、3%の運用利回りで運用した場合、126÷3=42となり、42年で元本が倍になると想定することができます。
複利を活かせる投資

これまで見てきたように、複利を活かすと投資効率が劇的に向上します。ここでは、そんな複利を活かして資産を増やせる投資手法をいくつかご紹介します。
不動産投資
ローンを組んで不動産投資をしている場合、ローン返済期間においては入居者からの家賃収入を借入金の返済に使うことが一般的になっており複利効果はあまり生じませんが、ローン完済後には、家賃収入を他の投資に充てることで、複利効果を得ることも可能です。
※当社は金融商品取引業者であり、不動産販売業者ではございません
iDeCo
iDeCoはつみたてNISAと並んで知名度の高い制度です。iDeCoを利用して投資信託等へつみたて投資することで複利効果を得ることも可能であるとともに、掛金の拠出時や運用益、そして給付を受け取るときに税制上の優遇措置を受けることができるというメリットがあります。
ただし、iDeCoは基本的に老後まで引き落としができないため、生活設計を誤らないようにしましょう。
まとめ

以上、複利運用のメリットやデメリット、おすすめの資産運用の方法について解説してきました。
投資において複利運用は効率的かつ基本的な考え方であり、この効果を活用しない手はありません。
今回ご紹介した簡便的な計算方法も参考に、目標から逆算して投資計画を立ててみてください。
2023年4月1日時点の情報をもとに作成。
本当のところ、現実の世界に複利なんてものはなくて、概念として存在するだけだよ。複利と言えばイメージしやすいから、金融機関は好んでこの言葉を使っている。とはいえ、複利の概念は非常に重要だし、再投資がそれに近いことは事実。

