贈与は、贈与する人(贈与者)と贈与を受ける人(受贈者)で成り立つ契約です。
教育資金の一括贈与とはその名の通り、教育に係る資金を受贈者に一括で贈与することを言いますが、一定の条件のもとで贈与税が非課税になる制度が存在します。
今回は、各種制度を利用することで教育資金の一括贈与を非課税で進める方法について解説していきます。
孫への教育資金を非課税で一括贈与する方法

お孫さんのために教育資金を一括贈与したくても、多額の贈与税が課される場合、想定通りの金額をお孫さんに贈与することができません。
そこで、贈与税を節税するために以下のような方法が検討できます。
教育資金の一括贈与の特例を利用する
教育資金の一括贈与の特例 は、正式名称を「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度」といいます。
教育資金の一括贈与の特例は、孫(子も含む)1人につき1,500万円 までの贈与(使途は教育費に限る)を非課税にするという制度です。
一括贈与というのは、1度しか贈与できないという意味ではなく、1500万円の上限内で認められる使途にかかる贈与であるならば分割して贈与することができます。
詳細については後述します。
暦年贈与する
暦年贈与を活用し、毎年110万円程度の金額を贈与する方法もあります。
暦年贈与には一定の非課税枠が設けられており、その年の1月1日から12月31日までの間における110万円までの贈与分が非課税になります。受贈者1人につき110万円までが上限となるため、複数の贈与者からの合計金額が110万円を超過する場合、超過部分については贈与税が課税されます。
この方法は一見手軽ですが、贈与者が亡くなると、亡くなるまでの3年以内 (2024年1月1日以降は7年以内)になされた贈与分が相続財産と見なされ、相続税の課税対象になる可能性があるなど、デメリットもあるため注意が必要です。
必要なときに都度教育資金を贈与する
必要なときに、必要な教育費用を子や孫に都度贈与する方法もあります。
この方法は最も手軽な方法であり、贈与税の課税対象にもなりませんが、本人が亡くなったり、病気などでやり取りが難しくなると贈与が受けられなくなるといったリスクもあります。
教育資金の一括贈与の特例の延長について

次に、教育資金の一括贈与の特例の延長について、最新の情報を解説します。
適用期間は2026年3月末に延長
教育資金の一括贈与の特例は、税制改正により適用期限が延長され、2026年3月31日まで有効とされています。
今後の税制改正でさらなる延長がなされるのかは不明なため、贈与の予定がある人は定期的に制度をチェックしておきましょう。
贈与する子や孫の年齢に注意
本制度は、受贈者である子や孫が30歳になると、原則として終了となるため注意が必要です。具体的には、以下のいずれかの場合に本制度の適用は終了となります。
- 受贈者が30歳に達した日(在学中・教育訓練給付金の対象となる教育訓練を受講している場合は最長40歳まで受贈可)に終了。
- 受贈者がその年中のいずれかの日において学校等に在学した日又は教育訓練を受けた日があることを、金融機関等の営業所等に届け出なかった場合。その年の12月31日に終了。
- 専用口座の残高がゼロになり、その専用口座に係る契約を終了させる合意があった場合。合意に基づく日に終了。
- 受贈者が死亡した場合。その受贈者が死亡した日に終了。
教育資金の一括贈与の特例を利用するための条件

教育資金の一括贈与の特例を利用し、贈与税を非課税にするには、以下の4つの条件をクリアしている必要があります。
①直系尊属からの贈与であること
教育資金の一括贈与の特例を利用する場合は、直系尊属(父母や祖父母、曽祖父母など)から子や孫などへの贈与である必要があります。
従って、血縁関係がない者からの贈与や直系尊属でない親族からの贈与は本制度の対象にはなりません。(民法 727 条に規定する養子縁組による親族関係がある場合を除く)
②金融機関に専用口座を開設すること
教育資金の一括贈与の特例を利用する場合は、金融機関に専用口座を開設し、そこで贈与を受ける必要があります。
この口座は、受贈者である子どもや孫1人につき1口座しか開設できない決まりになっています。あくまで受贈者1人につき1口座であり、複数の金融機関で口座を開設することはできません。
③領収書を提出していること
教育資金の一括贈与の特例を利用する場合は、登録した金融機関に教育費用に関する領収書を提出して、教育費用に関する出費と認められる必要があります。
専用口座から資金を非課税で引き出すには、手続きが必要であるということを認識しておきましょう。
④口座に預け入れた資金は使いきること
上述のとおり、教育資金の一括贈与の特例により非課税で教育資金を一括贈与できるのは受贈者が30歳になるまでの間です。そのため、登録した専用口座に預け入れた資金は、受贈者である子どもや孫が30歳になるまでに使いきる必要があります。
30歳になっても使いきれなかった場合には、残額に対して贈与税がかかる場合があるため注意が必要です 。
教育資金の一括贈与の特例における資金使途の範囲
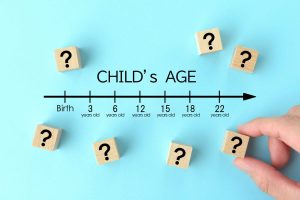
教育資金の一括贈与の特例は、資金使途の範囲が限定されており、範囲外の使途で資金を使用すると贈与税の対象となってしまう点に注意が必要です。
学校に直接支払う費用
学校等に対して直接支払われる費用に関しては、1500万円まで非課税枠の対象となります。
ここでいう「学校等」とは、以下のように分類されています。
- 学校教育法上の幼稚園、小・中学校、高等学校、大学、大学院、専修学校および各種学校
- 一定の外国の教育施設
- 認定こども園または保育所
対象となる費用は、以下の2種類に分類されます。
- 入学金、授業料、入園料、保育料、施設設備費または入学(園)試験の検定料など
- 学用品の購入費、修学旅行費や学校給食費など学校等における教育に伴って必要な費用など
広く教育で使う費用
広く教育で使う費用に関しては、500万円まで非課税の対象となります。
具体的には、以下のような費用が対象です。
- 教育(学習塾、そろばんなど)に関する役務の提供の対価や施設の使用料など
- スポーツ(水泳、野球など)または文化芸術に関する活動(ピアノ、絵画など)その他教養の向上のための活動に係る指導料金
- 教育に関する役務の提供、スポーツや文化芸術活動に使用する物品の購入に要する金銭
- 学校等以外に支払われる学用品の購入費、修学旅行費や学校給食費など学校等における教育に伴って必要な費用であり、学校等が必要と認めたもの
- 通学定期券代や留学のための渡航費・学校等に入学・転入学・編入学するために必要となった転居の際の交通費
教育資金の一括贈与にかかる注意点

教育資金の一括贈与の特例の活用を検討する場合、以下の点に注意が必要です。
受贈者の合計所得額が1000万円を超える場合
教育資金の一括贈与の特例を利用する場合は、受贈者である子や孫の前年の合計所得金額が1000万円以下である必要があります。
従って、1000万円を超える場合、他の要件をクリアしていても教育資金の一括贈与の特例を活用できないため注意が必要です。
年齢による制限
学校等に通っていない子や孫の場合、30歳になると教育資金の一括贈与の特例を活用できなくなります。
在学中の場合は最長40歳まで教育資金の一括贈与の特例を活用できますが、専用口座を開設した金融機関への届出が必要なので注意しましょう。
受贈者が23歳以上の場合資金の範囲が限定される
受贈者が23歳以上になると、教育資金の範囲は以下に限定され、他の習い事などに関する費用は非課税枠の対象外となります。
- 学校等に支払われる費用
- 学校等に関連する費用
- 教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講するための費用
まとめ

今回は、非課税で教育資金の一括贈与を行う方法について解説しました。
教育資金の贈与は、暦年贈与を活用したり、必要金額を都度贈与することもできますが、まとまった金額を贈与するのであれば教育資金の一括贈与の特例を活用するのがおすすめです。
ただし、今回ご紹介したように、教育資金の一括贈与には複数の条件があり、引き出しや使いきるまでのタイムリミットなども設定されているため注意は必要です。
条件や制限をよく理解した上で、家族にとって最善な贈与の方法を検討してみてください。
2023年7月1日時点の情報をもとに作成
生まれた環境によるね。
今後は親世代がお金を残さない(残せない)家庭も増えていくだろうから。
情報集めも大切だけど、自分の力を高めることの方が重要になるな。

