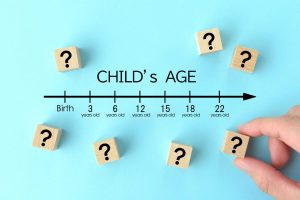子どもの教育資金は、どのように、いくら準備すれば良いのだろう。
そんな悩みを抱える方は多いのではないでしょうか。
そこで本記事では、教育資金の相場や、資金を準備するための具体的な方法について詳しく解説します。
大学までの教育資金はいくら?

準備すべき教育資金の目標額を決めるためには、まず教育費の相場を知ることからはじめましょう。
以下では、幼稚園から大学までにかかる教育費をご紹介します。
幼稚園から高校までに1800万円以上かかる場合も
文部科学省が公表している「令和3年度子供の学習費調査の結果について」によると、幼稚園から高校卒業までにかかる費用は、公立・私立で以下の通りとなっています。
| 学校 | 費用 |
|
| 公立 | 私立 | |
| 幼稚園 | 47.2万円 | 92.4万円 |
| 小学校 | 211.2万円 | 999.9万円 |
| 中学校 | 161.6万円 | 430.3万円 |
| 高校 |
154.3万円 |
315.6万円 |
私立・公立でケース分けした教育費は、それぞれ以下の通りです。
| ケース | 教育費総額 | |
| ケース1
全て公立に通った場合 |
574万円 | |
| ケース2
幼稚園は私立、小学校・中学校・高等学校は公立に通った場合 |
620万円 | |
| ケース3
幼稚園・高等学校は私立、小学校・中学校は公立に通った場合 |
781万円 | |
| ケース4
全て私立に通った場合 |
1838万円 | |
このように、子どもが公立に通うか私立に通うかで金額に大きな差があります。
特に子供がすべて私立に通った場合の教育費は1800万円を超えることが見込まれるため、相当な資金を準備する必要があるでしょう。
大学費用は800万円以上かかる場合も
日本政策金融公庫の令和3年度における「教育費負担の実態調査結果」によると、大学1年間にかかる教育費用は以下の通りです。
| 国公立 | 私立文系 | 私立理系 | |
| 入学費用 | 67.2万円 | 81.8万円 | 88.8万円 |
| 在学費用 | 103.5万円 | 152.0万円 | 183.2万円 |
入学費用と4年分の在学費用を計算すると、国公立で481.2万円、私立文系で689.8万円、私立理系で821.6万円になります。
つまり、上記の「幼稚園から高校まですべて私立の場合」であり、大学も私立理系の場合、2600万円以上の教育費が発生することになります。
子どもがまだ小さい場合、どのようなケースの進路を辿るのか予想するのは難しいものの、それぞれのケースにおける教育費の相場観を把握したうえで教育資金を準備していきましょう。
教育資金を準備する方法

教育資金を準備するには、以下のような方法があります。
無駄な出費を減らす
教育資金を準備するためにも、無駄な出費を減らすことを意識しましょう。
食費や交際費は、外食を減らしたり、飲み会に出席する回数を減らすことで削減できるかもしれません。
また、趣味にかける費用は、使い過ぎてしまわないよう毎月上限を決めておくと効果的です。
児童手当を将来の教育資金にする
児童手当は、中学校卒業までの子どもを養育する家庭に対して、国と地方自治体から支給される手当です。
児童手当は、子どもの年齢により以下のように変動します。
| 児童の年齢 | 児童手当の額(一人あたり/月) |
| 3歳未満 | 一律 1.5万円 |
| 3歳以上
小学校修了前 |
1万円
(第3子以降は1.5万円) |
| 中学生 | 一律 1万円 |
児童手当は教育資金として活用することができます。
たとえば、子どもが3月生まれの第1子の場合、生まれてから中学生に至るまでに児童手当だけで合計200万円前後のお金を受け取ることができます。
学資保険に加入する
学資保険は、教育資金の準備を目的として保険料を払込み、進学時にお祝い金として一定額を受け取りつつ、満期時には満期保険金を受け取る仕組みが一般的です。
また、学資保険は預貯金とは異なり、万が一の場合に備えた保障がセットになっているのが一般的です。
契約者が死亡したり、重度の障害を負ったりした場合に保険料の支払いが免除される特約を付加することができるため、万が一にも親が働けない状況になった場合でも子どもの教育資金を用意することができる点は学資保険のメリットと言えるでしょう。
学資保険は生命保険の1つとして扱われるため、「生命保険料控除」を受けられることも大きなメリットです。
生命保険料控除は、1年間に支払った保険料に応じて、税金計算上の所得金額から一定の金額が差し引かれるため、所得税などの税負担が軽くなります。
生命保険料控除は会社員なら年末調整時に、自営業者は確定申告時に申請することができます。
※個別の保険商品の設計や特約の有無等によって、本記事の記載内容とは異なる場合もありますのでご了承ください。
教育資金を準備するために投資も選択肢となる

以上のように、無駄な支出の節約、児童手当および学資保険を活用する方法もありますが、もうひとつの手段として、投資も活用して教育資金を準備することを検討してもよいでしょう。
ここでは、初心者でも手軽に始められる金融商品と、活用したい制度をご紹介します。
投資信託
投資信託は、複数の投資家から資金を集め、ファンドマネージャーという運用の専門家が投資家に代わって投資商品を分析/運用する金融商品です。
投資信託は手軽に投資することができ、専門知識を持たずとも分散投資をすることができるため、初心者にもおすすめの商品となります。
さらに、株式ファンドや債券ファンド、それらが複合されたバランスファンドなど、様々な種類の投資信託が存在し、自分の目標やリスク許容度に合わせて商品を選ぶことができるのも特徴です。
不動産投資信託
不動産投資信託(REIT)は、複数の不動産に少額から投資することができる投資信託です。
一般的に、不動産に投資するためには多額の費用が必要となります。
しかし、REITの場合は、多くの投資家から集めた資金でオフィスビルや商業施設、マンションなど複数の不動産などを購入し、その賃貸収入や売買益を投資家に分配する仕組みをとります。
投資家は少額のREITを購入するだけで、複数の不動産の間接的なオーナーとなることができます。
NISA制度
NISA制度とは、少額投資非課税制度のことを指します。通常、投資信託等に投資して利益が発生した場合、利益を確定させると20.315%の税金を支払わなければなりません。
しかし、NISAを活用すると、NISA口座内の取引であれば利益を確定させても非課税となります。
2024年から開始する新NISAは非課税期間が無制限になり、最大1800万円の投資元本まで非課税で運用することができます。
新NISAは教育資金を投資で準備することを検討する場合に活用したい有効な制度の一つとなります。
投資で教育資金を準備するうえでの注意点

投資で教育資金を準備する際は、以下の点に注意しましょう。
生活費には手を付けない
投資は余剰資金で行うことが鉄則となっています。
すぐに使う予定のある資金、例えば生活費を投資に回してしまうと、視点が短期的になってしまい、投資効率も悪くなります。
また、余剰資金を超えた金額を投資に回してしまうと、生活は当然苦しくなります。投資は生活費を除いた余剰資金で行うことが鉄則です。
つみたて投資を心がける
短期的に大きな利益を獲得することを期待して、リスクの高い投資商品に手を出すのは避けた方が良いでしょう。
投資の世界には短期的に大きな利益が獲得できることを謳う商品も存在しますが、それは同時に大きな損失が発生し得るということの裏返しでもあります。
教育資金は時間をかけてでも、堅実に準備すべき大切な資金であることを強く意識しましょう。
堅実な投資方法として、投資信託を毎月定額で購入するつみたて投資をおすすめします。
つみたて投資は市場の値動きにとらわれず一定のタイミングで投資し続けることになり、購入単価を平準化させる効果があります。
これを「ドル・コスト平均法」と呼びます。また、初心者が投資を習慣づけるためにも、つみたて投資は有効な投資手法であると言えるでしょう。
しかし、つみたて投資とはいえ、リスクの高すぎる投資信託を購入していては堅実な運用とは言えません。少なくとも、レバレッジ型の投資信託等、長期投資には向かない高リスクの投資信託への投資は、教育資金を準備することを目的とするならば避けるべきでしょう。
長期投資を心がける
投資をしていると、相場が動いた際にすぐにポジションを取りたくなったり、ポジションを持っていないと不安になる「ポジポジ病」という心理状態になることがあります。
このような短期的かつ感情的な取引は、長期で成長する市場経済からの恩恵を得られないだけでなく、心理的なストレスも抱えてしまうでしょう。
教育資金を投資で準備する場合は、余剰資金を使って長期投資を行うことが原則です。
もし短期的な値動きに心が揺れてしまう場合は、投資をはじめた本来の目的を再確認しましょう。
まとめ

教育資金を投資で準備するには、NISA等の非課税制度も上手く利用しながら、長期的な視点で臨むことが重要です。
今回ご紹介したように、子どもの教育費は2000万円を超える場合もあります。子どもの選択肢を確保するためにも、親が早くから教育資金の対策を行うことが重要となるでしょう。
※当社の取り扱う投資信託(さわかみファンド)は、2024年1月1日以降、新NISA(成長投資枠)の対象商品となる予定です。
2023年7月1日時点の情報をもとに作成
教育資金の準備に限らず、常に無駄の削減を心がけよう。その分、他にお金を回せるのだから。
お金と時間を有意義に使おう。