昨今、年金や社会保障制度の限界が明らかになる一方、長寿化によって老後の期間が長期化しています。
個人が自己責任で老後資金を準備することが求められるようになっているなか、一般的に老後に必要とされている金額が「2000万円」と言われています。
本記事では、老後2000万円問題の概要や資金のシミュレーション方法について解説し、老後2000万円問題に備えるための具体的な方法を紹介します。
老後2000万円問題とは?

老後2000万円問題は、金融庁の資料に端を発したキーワードですが、昨今の老後資金を考える上で重要なキーワードとなっています。
ここでは、老後資金2000万円問題の概要や前提となる世帯モデルについて解説します。
金融庁ワーキンググループによる試算
老後2000万円問題は、金融庁 金融審議会 市場ワーキング・グループ報告書 「高齢社会における資産形成・管理」の記載内容が物議を醸したことで話題になりました。
老後2000万円問題における2000万円とは、夫65歳以上、妻60歳以上の夫婦のみの無職世帯が30年間健康に生きた場合に予想される費用のことです。
老後2000万円必要な世帯のモデル
本報告書では、仕事を引退して年金生活に移行する中で毎月必要な費用を支払うと、毎月5万円ほど不足する状態になると報告されています。つまり、5万円×12ヵ月×30年で1800万円になり、約2000万円足りない計算となるのです。
当然、単身世帯や年金が通常より多くもらえる世帯、老後も仕事による収入がある世帯では、老後に必要な費用は抑えられるかもしれません。
老後に2000万円必要な理由

老後に2000万円必要になるという数字の背景には、以下のようなものがあげられます。
長寿化による影響
老後に資金が不足する背景のひとつに、長寿化があげられます。
金融審議会 市場ワーキング・グループ報告書 「高齢社会における資産形成・管理」によると日本人の平均寿命は伸び続けており、2017年の日本人の平均寿命は男性が81.1歳、女性が87.3歳となっています。
先述の想定世帯が「夫婦ともに90歳まで生きる」という状況は、一般的なモデルケースと考えることもできるでしょう。
このように、長寿化とそれに伴う老後の長期化により、必要な生活費はより増大しているのです。
退職金の減額による影響
退職金の減額も老後2000万円問題に大きな影響を及ぼしています。
日本では長く続く経済の停滞により、かつてのように老後の生活費を賄うだけの退職金をもらえない人が増えています。
また、今後も企業の退職給付額の減少傾向が続く可能性があります。
こうした中では、年金の不足額が多くなり、自力で用意しなければならない資金が増えるのも当然といえます。
教育費の支払いによる影響
教育費の支払いも老後資金の不足に影響を及ぼす要因のひとつです。
文部科学省の「子供の学習費調査」では幼稚園から高校までの15年間の学費が、日本政策金融公庫の「教育費負担の実態調査」では大学の学費がそれぞれ調査されています。
| 国公立 | 私立 | |
| 幼稚園 | 約47万円 | 約92万円 |
| 小学校 | 約211万円 | 約1000万円 |
| 中学校 | 約162万円 | 約430万円 |
| 高校 | 約154万円 | 約316万円 |
| 大学 | 約481万円 | 約690万円(文系)
約822万円(理系) |
| 合計 | 約1,055万円 | 約2528万円(文系)
約2660万円(理系) |
※令和3年度のデータ
このように、子どもが大学まですべて国公立に進学したとしても1,000万円以上の教育費が必要になってきます。
さらに子どもが2人以上いると、数千万円の支払いを余儀なくされるため、子どもの教育が終わった50代頃には、老後に蓄える資金が底をついているケースも多いのです。
こうした状況に陥らないためには、あらかじめ老後資金がいくら必要かシミュレーションすることが重要です。
老後資金のシミュレーション

老後資金をしっかり把握し、若いうちから資産形成をするためには、老後資金のシミュレーションからはじめることをおすすめします。ここでは、老後資金のシミュレーション方法を項目別に紹介します。
年金受給見込み額の試算
まずは、老後にもらえる年金受給見込み額の試算からはじめましょう。
令和5年度の国民年金月額は66,250円が満額となっています。
また、夫婦2人分の老齢基礎年金を含んだ標準的な厚生年金額は224,482円です。
これらはあくまで一般的な金額であり、厚生年金などは年収によっても金額が変わります。
退職金の試算
会社から退職金が支給される場合は、退職金額も計算のうちに入れておきましょう。
東京都産業労働局の「中小企業の賃金・退職金事情(令和4年版)」によると、高校卒は約994万円、大学卒では約1092万円の退職金が支給されることが想定されています。
これらは企業や勤続年数によっても大きく変わるため、自分の会社に当てはめて計算してみましょう。
老後の生活費の試算
金融審議会 市場ワーキング・グループ報告書 「高齢社会における資産形成・管理」によると、夫婦無職世帯で平均的な老後生活を継続するために必要な日常生活費は月額平均263,718円となっています。
夫婦2人でゆとりある老後生活をするには、日常生活プラスアルファの金額が必要となります。
自分たちがどのような生活を送りたいのか想像しながら、ゆとりを持った生活費を計上しましょう。
必要な老後資金の試算
最低限必要な老後の生活費が月263,718円であるため、年金や退職金、その他の収入でこの必要な生活費を上回れば老後資金問題はひとまずクリアできていることになります。
ただし、老後は思わぬ支出も発生するものです。たとえば、孫へのおこづかいや子どもの結婚資金、家やマンションの修繕費など、単発での出費も考慮しなければなりません。
このように、必要生活費と収入がプラスマイナスゼロの状態では、急な出費に対応できません。必要生活費よりややゆとりをもった老後資金の設計が必要です。
老後に2000万円も貯められない!対策法は?

金融広報中央委員会が発表した家計の金融行動に関する世論調査(令和3年)によると、60代の2人以上世帯では、金融資産保有額が2427万円、中央値は810万円となっています。
ただし、平均値は富裕層の貯蓄額・金融資産保有額に大きく影響を受けて引き上げられていると考えられるため、実際には中央値である810万円あたりが一般世帯の貯蓄額と考えられるでしょう。
このように、多くの世帯で「老後2000万円問題」をクリアできていない状況が見受けられます。
では、老後に2000万円貯められそうにない世帯は、どう対処すれば良いのでしょうか。ここでは、いくつか対処法を検討してみましょう。
老後の生活費を減らす工夫をする
当然ですが、老後の貯蓄が足りないなら、あらかじめ生活費を減らす工夫が必要になります。たとえば、豪華な家のリフォームをやめる、外食を控える、できるだけ徒歩で買い物に行くなど、日常の中で無駄遣いがないかを検討し、節約することが大切です。
iDeCoを活用する
iDeCoは、国民年金や厚生年金といった公的年金とは別に給付を受けられる私的年金制度の一種であり、自分が拠出した掛金を運用し、資産を形成することが可能です。
基本的に20歳以上65歳未満までしか運用できませんが、掛金が全額所得控除されること、確定拠出年金制度内での運用益が非課税で再投資できること、 受給時も税制優遇を受けられることなど、老後資金の形成にはメリットが大きい制度です。
20年後、30年後の老後資金に不安を持っている人は、ぜひ一度検討してみてください。
不動産投資をする
不動産投資も老後資金の形成に選ばれやすい手法です
不動産投資は多くの場合ローンを組んで物件を購入し、家賃収入からローンの返済をします。
若いうちに不動産投資のローンを組んでおけば、老後にはローンも完済した状態で家賃収入を純粋に収益として受け取ることができるようになるため、年金代わりになり、老後資金の足しにできます。
ただし、不動産投資にはある程度元手を用意する必要があるため、資金の余裕があれば検討してみましょう。
※当社は金融商品取引業者であり、不動産販売業者ではございません
まとめ
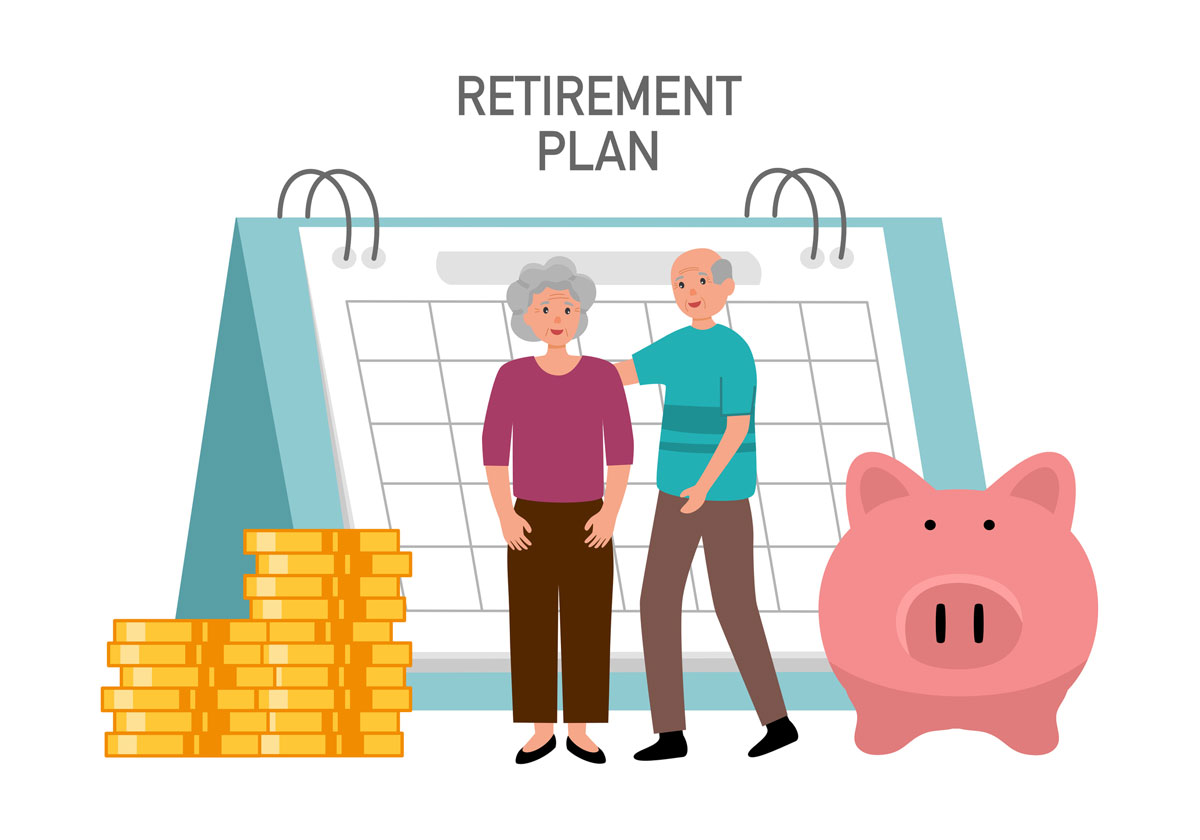
老後2000万円問題は、当時多くの人々が衝撃を受け、老後資金の重要性を再認識するきっかけとなりました。
しかし、老後の資金額は、世帯や雇用形態、生活水準などによって大きく異なります。
まずは自分たちに必要な老後資金をシミュレーションし、資産運用なども検討しながら老後資金を形成していきましょう。
2023年4月1日時点の情報をもとに作成
老後2000万円問題は「国民のお金を投資に振り向ける」金融庁の煽りの発言だったけれど、実際、2000万円では足りない可能性もある。ただ、現役時代の収入や生活水準が老後に必要な資産額を決定づけるので、あまり真剣に考えなくても良いのではないかな。

