近年、高齢者の老後資金に関するニュースが多く報じられています。
年金支給額が減少する中で、豊かな老後を生きるには、引退前に資金を準備しておく必要があります。
そのためには、自身の老後にどの程度お金が必要なのかシミュレーションしておくことが重要です。
本記事では、老後に必要な生活費のシミュレーション方法や老後資金が不足する場合の対処法についてご紹介します。
老後に必要な生活費はいくら?

老後に必要な生活費は、年金の支給金額や貯蓄の状況によって異なります。そこでまずは、老後に必要な生活費をシミュレーションしてみましょう。
老後は独身で145,000円程度必要
令和3年の総務省統計局の家計調査年報(家計収支編)によると、65歳以上の単身無職世帯では145,000円程度の生活費が必要とされています。
毎月の生活費の内訳は以下のとおりです。
| 項目 | 独身 |
| 食料 |
36,322円 |
| 住居 |
13,090円 |
| 光熱・水道 |
12,610円 |
| 家具・家事用品 |
5,077円 |
| 被服および履物 |
2,940円 |
| 保健医療 |
8,429円 |
| 交通・通信 |
12,213円 |
| 教育 |
0円 |
| 教養娯楽 |
12,609円 |
| その他の消費支出 |
29,185円 |
| 非消費支出(税金や保険料など) |
12,271円 |
| 合計 |
144,746円 |
1ヶ月145,000円とすると、1年間で174万円、20年間で3,480万円、30年間で5,220万円必要です。
ただし、年金受給開始年齢は将来的に延長されることも予想されているため、これらの金額は現時点での最低限必要となる資金と理解しておきましょう。
夫婦2人の老後は255,000円程度必要
同調査によると、65歳以上の夫婦のみの無職世帯の老後に必要な生活費は255,000円程度とされています。
具体的な生活費の項目は以下の通りです。
| 項目 | 夫婦 |
| 食料 |
65,789円 |
| 住居 |
16,498円 |
| 光熱・水道 |
19,496円 |
| 家具・家事用品 |
10,434円 |
| 被服および履物 |
5,041円 |
| 保健医療 |
16,163円 |
| 交通・通信 |
25,232円 |
| 教育 |
2円 |
| 教養娯楽 |
19,239円 |
| その他の消費支出 |
46,542円 |
| 非消費支出(税金や保険料など) |
30,664円 |
| 合計 |
255,100円 |
1ヶ月255,000円とすると、1年間で306万円、20年間で6,120万円、30年間で9,180万円必要です。
年金受給開始年齢が65歳だとすると、20年間で85歳となります。夫婦2人が65歳で年金受給を開始してから、日本人の平均寿命である85歳程度まで不自由なく生活していくためには、想定される支出金額である6,120万円を年金や預貯金、その他の収入等で賄う必要があるということです。
老後に得られる収入
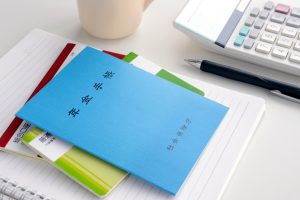
老後に得られる収入は、主に公的年金の収入でしょう。会社員・自営業者それぞれがもらえる年金額は以下の通りです。
会社員がもらえる公的年金
厚生労働省の「令和3年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況 」によると、厚生年金に加入している会社員の年金支給額は月平均で約146,000円でした。
先に「老後は独身で145,000円程度必要」、「夫婦2人の老後は255,000円程度必要」としたとおり、厚生年金の月平均支給額を夫婦二人で受給できれば生活費を賄えますが、一部の家庭では厚生年金の収入だけでは不足することも考えられます。
厚生労働省では、情報を入力するだけで将来の年金受給額を試算できる「公的年金シミュレーター」を公開しています。
例えば、それぞれ以下の条件の夫婦の場合、年金シミュレーターでは以下の年金支給額となります。
【夫婦共働きの場合】
| 夫 | 妻 | |
| 年齢 | 60歳 | 58歳 |
| 雇用形態 | 正社員 | 正社員 |
| 年収 | 650万円 | 400万円 |
| 年金支払い年数 | 20歳~65歳 | 20歳~65歳 |
| 就労完了年齢 | 65歳 | 65歳 |
| 年金受給開始年齢 | 65歳 | 65歳 |
| 年金受給額 | 247万円/年 | 184万円/年 |
【夫が正社員・妻がパートで、ともに60歳で退職した場合】
| 夫 | 妻 | |
| 年齢 | 60歳 | 58歳 |
| 雇用形態 | 正社員 | パート |
| 年収 | 650万円 | 110万円 |
| 年金支払い年数 | 20歳~59歳 | 20歳~59歳※付加納付なし |
| 就労完了年齢 | 60歳 | 60歳 |
| 年金受給開始年齢 | 65歳 | 65歳 |
| 年金受給額 | 214万円/年 | 80万円/年 |
自営業がもらえる公的年金
厚生労働省の同調査によると、国民年金にのみ加入している自営業者の場合、年金支給額は月平均で約56,000円でした。
これは1年間で約67万円、20年間で約1,344万円、30年間で約2,016万円となります。
自営業者は国民年金の1階建て部分のみの給付となるため、老後資産の準備がなければ厳しい老後の生活が迫られます。
公的年金だけでは老後の生活費が足りない場合は?

公的年金の受給だけで老後の生活費を賄うことができればそれに越したことはありませんが、実際は多くの方が資金不足に見舞われるのが現実です。そこで、公的年金だけでは老後の生活費が足りなくなる場合を想定し、その対処法について考えていきましょう
支出を減らす方法を考える
老後に必要な生活費を正確に把握するためには、まずは自分のライフプランを作成することが大切です。その上で、収入や資産状況を洗い出し、必要な生活費を算出しましょう。
ライフプランと自分の収入および資産状況を算出してみると、実は生活費が足りなくなってしまう、というケースも考えられます。その場合は、以下のような対処法があります。
- 支出を見直す:生活費を減らすために、必要のない支出を見直してみましょう。例えば、高額な趣味や贅沢品の購入を控えるなどが挙げられます。
- 副業を始める:老後に限らず、副業を始めて収入源を増やすことも検討してみましょう。自分のスキルや経験を活かして、定年後もアルバイトやフリーランスとして働くのも一つの方法です。
- 資産運用をする:貯蓄だけでなく、資産運用に取り組むことで老後資産を増やすことも検討してみましょう。ただし、リスクや手数料などを考慮して、自分に合った運用方法を選ぶことが大切です。
老後に備えるためには、計画的に行動することが大切です。自分に合った方法で、しっかりと準備しておきましょう。
再就職する
老後に再就職することで、労働収入を得ることができます。例えば、65歳から70歳まで再就職で働けば、老後の5年間はその収入を頼りにすることもできます。
ただし、再就職後の収入は引退前の収入より減少することが一般的です。ライフプランを作成するうえでは再就職後の収入は保守的な金額を想定しておきましょう。
老齢年金の繰下げ受給を選択する
老齢年金の繰下げ受給とは、老齢年金を受給する際に、受給開始年齢を遅らせることでより多くの年金を受け取る方法です。この方法は、老後の生活に備えるための一つの選択肢でしょう。
年金を繰下げ受給する場合は、その分後から貰える年金額が増額されます。そのため、例えば70歳まで働く人であれば、受給開始年齢を70歳以降に繰り下げて、貰える年金を増やすのも手です。
日本年金機構によると、70歳まで年金の受給を繰下げた場合の増額率は42.0%、75歳の場合の増加率は84.0%となっています。年金受給開始年齢を超過しても健康に働ける場合は、こうした制度を利用しても良いでしょう。
iDeCoを利用する
iDeCo(個人型確定拠出年金)を利用すると、老後の生活費の足しとなる収入(または資産)を得ることが期待できます。iDeCoは、個人で加入することができる年金制度の一種であり、投資信託などの金融商品に投資することで将来の年金収入(または退職一時金)を増やすことを目的としています。拠出金額に応じた所得控除を受けることができるとともに、利息や運用益にかかる税金が非課税になります。
また、iDeCoで運用した資産を年金給付形式で受け取る場合は公的年金等控除を受けることができ、一時金として受給する場合は退職所得控除を受けることができます。このことから、iDeCoは老後資金を準備するために活用したい有効な制度の一つとなります。
NISAを利用する
NISAは、少額投資非課税制度です。通常は投資信託等に投資して利益が発生した場合、20.315%の税金を支払わなければなりません。しかし、NISAを活用すると、NISA口座内の取引であれば利益が発生しても非課税となります。2024年から開始する新NISAは非課税期間が無制限になり、1800万円の投資元本まで非課税で運用することができます。制度の対象となる金融商品に一定の制限がありますが、新NISAは老後資金を準備するために活用したい有効な制度の一つとなります。
まとめ

老後に必要な生活費は、独身で月145,000円程度、夫婦2人で255,000円程度必要です。また、長生きすればするほど、その生活費を賄うための資産は多く必要となってきます。
このように、老後の生活は公的年金だけで賄える人は少なく、不足分を補うには対策が必要です。具体的には、節約や再就職、年金の繰下げのほか、投資による資産運用があげられます。
今回紹介したように、さまざまな制度を利用しながら、賢く老後の対策をしていきましょう。
※当社の取り扱う投資信託(さわかみファンド)は2024年1月1日以降、新NISA(成長投資枠)の対象商品となる予定です。
2023年6月1日時点の情報をもとに作成
シミュレーションは価値がないというか、使えないオモチャだよね。
物価変動や情勢を捉えないと、実態にそぐわないものとなる。
一般的に言われる支出額は参考にするべき材料。ただし、未来は確実に変わるので、常に現在のムダな支出を減らしつつ、余裕をもって考えておきたい。

